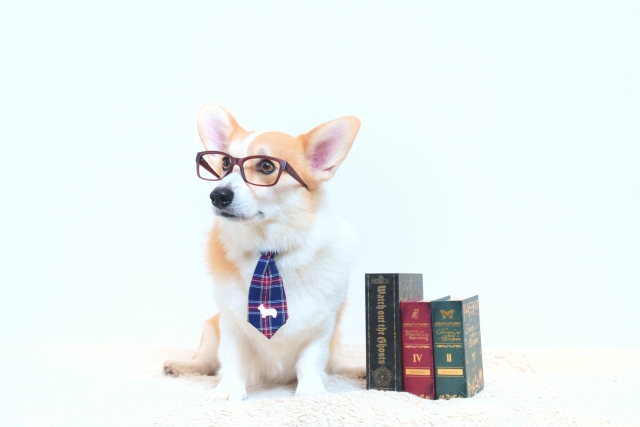「災害が起きてもうちの子は大丈夫」そう思っていませんか?
災害時、愛するペットたちは自ら身を守れるわけでも飼い主さんを安全な場所に導いてくれるわけでもありません。いつ起こるかわからない自然災害から愛犬を守るためには、飼い主である私たち人間が事前の備えを万全にしておくことが重要です。(人間用の備蓄に+αしてペット用の防災を考える必要があります!)
特に災害時はペットよりも人間の方が優先されがちですので、ペット物資の配給は人間の配給よりとても遅れる可能性が非常に高く、それを見越して対策をしておくことが必要です。
この記事では、地震や台風などの災害時に備えて、必要な防災グッズや安全に避難するための注意点、被災状況別の注意点などを具体的に解説します。愛犬と飼い主さんの両方が安心して災害に備えることができますように。
愛犬を守る防災の重要性
「ペットは家族」と考える方が増える一方で、災害時に愛犬を守るための備えが十分でないケースも見られます。ここでは、愛犬を守る防災の重要性について、具体的な例を交えながら解説します。
災害時、愛犬はいつも以上に危険にさらされる
災害発生時は、愛犬にとって安全な住環境が脅かされるだけでなく、様々な危険に遭遇する可能性があります。
迷子や脱走のリスク増加
地震の揺れや大きな音に驚いてパニックになり、リードを振り切って逃げてしまうことがあります。また、避難の混乱の中で飼い主とはぐれてしまい、迷子になってしまうケースも後を絶ちません。
現にうちの子は、(災害時ですらない平時に)いつもと違う自ら散歩コースに喜び勇んで進んで行った結果、電車(と踏切の音)に驚いて逃げました。(首輪とリードはしっかりつけていましたが、”火事場の馬鹿力”で千切って逃げてしまいました⇒結果的には無事ひとりで自宅に帰ってきましたが、見失ってしまった時にはとても焦りました⇒その後、再発防止のために脱出しにくいハーネスを購入しました)
住環境の変化によるストレス
慣れ親しんだ家が被害を受けたり、避難所生活を送ることで、愛犬は大きなストレスを感じます。環境の変化による不安や恐怖から、食欲不振、下痢、嘔吐などの症状が現れることも少なくありません。
怪我や病気のリスク
倒壊した建物や散乱したガラス片など、災害発生直後は危険物が多く、愛犬が怪我をしてしまう可能性があります。また、避難所など不衛生な環境下では、感染症のリスクも高まります。
「うちの子は大丈夫」は危険!
「うちの犬は大人しいから大丈夫」「そもそも災害なんてめったに起こらないから大丈夫」と考えていませんか?
しかし、災害はいつどこで発生するか分かりません。
また、普段は大人しい犬でも、予期せぬ事態に遭遇することでパニックを起こし、予期せぬ行動をとってしまう可能性があります。そもそも、飼い主さんが在宅でないときに自然災害が発生することもあります。
愛犬の安全を守るためには、「うちの子は大丈夫」という安易な考えや過信を捨てて、日頃から災害に備えておくことが重要です。
| 考慮事項 | 具体的な例 | 備えておくべきこと |
|---|---|---|
| 犬の性格 | 普段は大人しい犬でも、大きな音や見慣れない場所にパニックになる可能性あり。 | 愛犬の性格や行動のくせや特徴を理解しておく。 どのような状況でパニックを起こしやすいか把握しておく。 |
| 健康状態 | 持病がある場合、避難生活の中で症状が悪化したり、必要な薬が手に入らないことが心配。 | 愛犬の健康状態を日頃から把握し、必要に応じて獣医師に相談しておく。 常備薬なども用意しておく。 |
| 飼育環境 | ケージに慣れていないと、災害時の避難の際に苦労する可能性あり。 | 日頃からケージに慣れておく。 災害時を想定した飼育環境を整えておく。 |
愛犬を守るためには、飼い主が責任を持って防災対策を行うことが重要です。日頃から災害を想定し、いざという時に愛犬を守れるよう、しっかりと準備しておきましょう。
愛犬用防災グッズ:備えあれば憂いなし!
「うちの子は大丈夫」ではなく、いざという時のために、愛犬を守る防災グッズを準備しておきましょう。備えあれば憂いなしです!
防災グッズの準備は「いつもの」と「もしもの」をセットで
愛犬用の防災グッズは、「いつもの」生活で使っているものと、「もしも」災害が起こった時に必要なものをセットで準備することが大切です。環境の変化で体調を崩しやすくなる愛犬のために、普段使い慣れたものを用意してあげましょう。
繰り返しになりますが、災害時はペットよりも人間の方が優先されがちですので、ペット物資の配給は人間の配給よりとても遅れる可能性が非常に高いです。ペット用品の入手が困難になってしまっても大切な愛犬の命を繋ぐことができるよう、備蓄しておくことが望ましいです。愛犬を守ることができるのは飼い主さんだけです。
とくに持病やアレルギーがあって特別な療養食を食べている子がいる場合は、余裕を持って2ヶ月分のストックがあると安心ですよ。
食事編:最低3日分+αの備蓄を
災害時は、ペットフードの入手が困難になる可能性があります。人間と同様、最低でも3日分、できれば5日~7日分のフードを備蓄しておきましょう。(特別な療養食を食べている子がいる場合は、余裕を持って多めに確保しておきましょう。救援物資の中に合うものがあるとは限らないからです)
ただでさえ慣れない環境下では食欲が出ず、体調を崩してしまいがちなのは人間も犬も同じです。
緊張したり強い恐怖を感じたりすると、ごはんを食べなくなってしまったり、水を飲まなくなってしまう子も多いそうです。普段食べ慣れているドッグフードしか食べない場合もあります。可能なら、色々なタイプのフードを備蓄しておいてあげると「もしもの時」の力強い味方になりますよ。
| 種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ドライフード | 水分含有量が少なく、長期保存に適しています。 | 普段から食べ慣れているものを選びましょう。 |
| ウェットフード | 水分補給と食欲増進に役立ちます。 | 開封後は早めに使い切りましょう。 |
| 缶詰 | 長期保存が可能で、非常時にも与えやすいです。 | 種類が豊富なので、愛犬の好みに合わせて選びましょう。 |
| おやつ | 愛犬のストレス軽減に役立ちます。 | 与えすぎには注意しましょう。 |
愛犬の年齢や健康状態を考慮し、必要な栄養素を満たせるものを選びましょう。
また、フードを湿気から守るために、密閉容器に入れたり、乾燥剤を入れたりして保管しましょう。賞味期限切れにも注意し、定期的に交換することが大切です。(これを「ローリングストック」といいます)
水編:飲み水だけでなく、衛生面も考慮して
水は、愛犬の生命維持に欠かせません。飲み水だけでなく、食器洗い、トイレの処理などにも使用することを考慮し、人間同様、1日あたり3リットルを目安に、最低でも3日分、できれば5日~7日分の水を備蓄しておきましょう。
- 飲料水
- ウォーターボトル
- 携帯用浄水器
- 折りたたみ式の水飲みボウル
水は、常温で保管できるペットボトル水が便利です。停電時でも使用できるよう、ウォーターボトルも用意しておくと安心です。また、衛生面を保つために、携帯用浄水器があると便利です。飲み水とは別に、体を拭いたり、トイレを流したりするための水も用意しておきましょう。
排泄編:ペットシーツやトイレ用品は多めに
災害時は、いつも通りにトイレの処理ができない場合があります。ペットシーツやトイレ用品は多めに準備しておきましょう。消臭効果の高いものを選んだり、使用済みペットシーツを入れるためのゴミ袋を用意しておいたりするのもおすすめです。
- ペットシーツ(レギュラー、ワイド、スーパーワイドなど、愛犬の体格に合わせたサイズ)
- トイレトレー
- 消臭剤
- ゴミ袋
ペットシーツは人間のトイレの代用品にもできますので、我が家では、セールのときにまとめ買いして多めに備蓄していますよ。防臭袋も重宝しています。
避難所によっては、ペットの受け入れにあたり、トイレのしつけが条件になっている場合があります。
日頃から、愛犬にトイレの習慣を身につけさせておくことが重要です。また、災害発生時は、環境の変化によるストレスで、トイレの失敗が増える可能性があります。愛犬の様子をよく観察し、優しく声をかけながら落ち着けるようにサポートしてあげましょう。
健康管理編:常備薬や消毒液があると安心
愛犬が普段から服用している薬がある場合は、必ず多めに準備しておきましょう。また、災害時は怪我をするリスクも高まるため、消毒液や包帯などの応急処置用品があると安心です。
- 常備薬(飲み薬、塗り薬など)
- 健康記録簿(ワクチン接種記録、アレルギー情報など)
- 消毒液
- ガーゼ
- 包帯
愛犬の健康状態を把握するために、日頃から健康記録簿をつけておくことをおすすめします。ワクチン接種記録やアレルギー情報などをまとめておくと、いざという時に役立ちます。また、災害時は動物病院の診療が制限される場合もあるため、あらかじめ、近隣の動物病院の情報を事前に確認しておきましょう。
避難生活編:首輪・リード、ケージがあると安心
避難する際に、愛犬が逃げ出してしまうことを防ぐため、首輪やリードは必ず着用させましょう。また、避難所では、他の動物や人とのトラブルを避けるため、ケージがあると便利です。普段からケージに慣れておくことで、愛犬のストレスを軽減することができます。
- 首輪(サイズが合っていることを確認)
- リード(伸縮性のないもの)
- ケージ(愛犬が中で方向転換できる程度の大きさ)
- クレート
- キャリーバッグ
首輪には、迷子札を必ずつけ、飼い主の連絡先を記入しておきましょう。マイクロチップの装着もおすすめです。避難所では、スペースが限られている場合もあります。折りたたみ式のケージやクレート、キャリーバッグなども検討しておくと良いでしょう。
その他:愛犬の情報をまとめたもの
愛犬の写真、特徴、健康状態などをまとめたものを用意しておきましょう。迷子になった際に役立ちます。
- 愛犬の写真(全身、顔のアップなど複数枚)
- 愛犬の特徴(犬種、毛色、性別、年齢、体重、性格、鑑札番号、マイクロチップ番号など)
- 健康状態(持病、アレルギー、ワクチン接種歴など)
- 飼い主の連絡先
これらの情報は、スマートフォンなどに保存しておくと便利です。また、印刷して防災グッズと一緒に保管しておくと、万が一スマートフォンの充電が切れた場合でも安心です。
防災グッズを選ぶ上での注意点
愛犬用の防災グッズを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
愛犬の年齢や体格に合ったものを選ぶ
愛犬の年齢や体格に合ったサイズの首輪やリード、ケージを選びましょう。特に子犬や老犬は、体に負担がかかりにくいものを選ぶことが大切です。フードも、年齢や健康状態に合わせたものを選びましょう。
定期的な点検と交換を忘れずに
防災グッズは、定期的に点検し、必要に応じて交換しましょう。特に、フードや水は賞味期限切れに注意が必要です。また、首輪やリードは劣化していないか、ケージは破損していないかを確認しましょう。
愛犬と安全に避難するために:知っておきたいこと
災害発生時は、人にとってもペットにとっても混乱する状況です。愛犬と安全に避難するため、日頃からの備えや避難時の注意点を押さえておきましょう。
愛犬と安全に避難するための心得
日頃から避難経路の確認を
避難が必要になった際に、慌てずに安全な場所に移動できるよう、日頃から避難経路を確認しておきましょう。お住まいの地域のハザードマップを確認し、洪水、土砂災害、津波などのリスクを把握しておくことが重要です。また、実際に愛犬と一緒に避難経路を歩いてみることをおすすめします。その際、ペット可の公園や避難所など、安全に休憩できる場所も確認しておくと安心です。
愛犬の情報を分かりやすく表示
災害時、飼い主とはぐれてしまう可能性もあります。首輪に迷子札を付け、愛犬の名前、飼い主の連絡先、住所などを記載しておきましょう。マイクロチップの装着も有効です。また、ケージやキャリーバッグにも同様の情報を記載したものを貼っておくと、より安心です。
災害時のペット同行避難について
災害時のペット同行避難は、飼い主の責任において行うことが原則です。避難所によってはペットの受け入れができない場合もあるため、事前に確認が必要です。各自治体のホームページや、地域の窓口に問い合わせてみましょう。避難先では、他の避難者への配慮を忘れず、トラブルを避けるためにも、普段からしつけや健康管理をしておくことが大切です。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 同行避難の原則 | 飼い主の責任において行う |
| 避難所のペット受け入れ | 事前に確認が必要(自治体HP、地域窓口で確認) |
| 避難先での注意点 | しつけ、健康管理、他の避難者への配慮 |
避難訓練のススメ
愛犬と安全に避難するためには、日頃からの訓練が重要です。突然の災害時に落ち着いて行動できるよう、以下のポイントを参考に、定期的な訓練を行いましょう。
クレートやキャリーバッグに慣れさせる
避難時は、クレートやキャリーバッグを利用することで、愛犬を安全に運ぶことができます。日頃からクレートやキャリーバッグに慣れさせておくことで、愛犬のストレスを軽減できます。おやつやおもちゃを与えたり、クレートやキャリーバッグの中で休ませたりする時間を設け、安心できる場所と認識させましょう。また、災害時は長時間の移動になることも予想されるため、普段から短時間でもクレートやキャリーバッグに入る練習をしておくことが大切です。
首輪やハーネスの装着練習
普段から首輪やハーネスを着用していない場合は、避難時に嫌がったり、暴れたりする可能性があります。日頃から首輪やハーネスを着用し、散歩などを通して慣れさせておきましょう。装着する際は、締め付けすぎないように注意し、愛犬の体格に合ったものを選びましょう。
騒音や人混みに慣れさせる
避難所など、多くの犬や人が集まる場所では、愛犬が大きなストレスを感じてしまうことがあります。普段から、他の犬や人との適切な距離感を保ちながら、公園やドッグランなどで社会性を身につけさせておくことが重要です。また、掃除機の音や車の音など、様々な音に慣れさせておくことも有効です。
被災状況別の注意点:状況に合わせた行動を
災害はいつ起こるか分かりません。愛犬を守るためには、それぞれの災害の特徴を理解し、状況に合わせた適切な行動をとることが重要です。ここでは、地震、台風、洪水の際に特に注意すべき点に着目してそれぞれ解説します。
地震発生時の注意点
地震発生時は、まず身の安全を確保することが最優先です。その上で、愛犬を守ために以下の点に注意しましょう。
揺れがお落ち着くまで、愛犬を安全な場所に誘導する
家具の転倒や落下物から愛犬を守るため、テーブルの下や部屋の隅など、少しでも安全な場所に誘導しましょう。落ち着いて行動することが大切です。飼い主さんがパニックを起こすと、愛犬にも伝染し、思わぬ事故につながる可能性があります。愛犬を落ち着かせるように優しく声をかけながら、安全な場所へ誘導してください。
また、愛犬がパニックになって逃げ出さないよう、リードやハーネスを装着しておきましょう。もしもの時に備え、日頃からクレートトレーニングをしておくことも有効です。クレートに慣れていれば、愛犬にとって安全な空間となり、避難時も安心できます。
| 状況 | 行動 |
|---|---|
| 室内にいる時 | テーブルの下や部屋の隅など、安全な場所に誘導する。 リードやハーネスを装着しておく。 |
| 屋外にいる時 | 建物や電柱、ブロック塀など、倒壊する危険性のあるものから遠ざける。 リードをしっかり持つ。 |
| 散歩中 | 抱き上げられる場合は抱き上げる。 そうでない場合はリードを短く持って、周囲の安全を確認する。 |
二次災害への備えも忘れずに
地震発生後は、ガス漏れや火災の発生、津波の襲来など、二次災害の危険性があります。周囲の状況に注意し、必要に応じて避難の準備を進めましょう。避難する際には、愛犬も一緒に連れて行けるよう、キャリーバッグやケージなどを用意しておくと安心です。
台風接近・上陸時の注意点
台風による強風や豪雨は、愛犬にとって大きな脅威となります。台風接近前から早めの対策を心がけましょう。
強風対策
- 窓やベランダなど、風で物が飛んでくる可能性のある場所には近づけないようにする。
- 庭に繋いでいる場合は、室内に避難させるか、頑丈な場所に繋ぎ直す。
豪雨対策
- 散歩は控え、やむを得ず外出する場合は、レインコートなどを着用させる。
- 浸水しやすい場所に住んでいる場合は、事前に避難場所を確認しておく。
洪水発生時の注意点
洪水が発生した場合、愛犬は濁流に流されたり、水没したりする危険性があります。早めの避難を心がけ、以下の点に注意しましょう。
愛犬を抱きかかえるか、リードをしっかり持って避難する
洪水の中を歩くのは危険なので、愛犬を抱きかかえるか、リードをしっかり持って避難しましょう。(成人した人間でも膝の高さまで水があるところでは簡単に流されます)⇒水の流れが速い場合は、無理に渡ろうとせず、安全な場所に避難してください。
避難場所では、愛犬の健康状態に注意する
避難場所では、愛犬が体調を崩さないよう、清潔な水やフードを与え、ストレスを軽減できるよう努めましょう。また、他の動物との接触による感染症にも注意が必要です。ワクチン接種やノミ・ダニ予防など、日頃からの健康管理も大切です。
愛犬の防災オススメ書籍
まとめ
大切な愛犬を災害から守るためには、日頃からの備えが重要です。水やドッグフードなどの防災グッズは、愛犬の年齢や体格に合わせて準備し、定期的な点検と交換を忘れずに行いましょう。避難時は、安全確保のため、首輪やリードを着用させ、状況に応じてケージを使用することも検討しましょう。また、自治体のペット同行避難情報を確認しておくことも大切です。日頃からの備えと、冷静な状況判断によって、愛犬と安全に災害を乗り越えましょう。